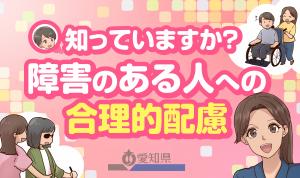本文
愛知県障害者差別解消推進条例について
条例の概要
この条例は、平成28年4月施行の障害者差別解消法の趣旨を、広く県民の皆様に周知し、県民各層の差別の解消推進への気運を高め、県民一体となって、障害を理由とする差別の解消の推進を図ることを目的として、基本理念を定め、その下に、県、県民、事業者の責務を明らかにしています。(平成27年12月18日制定、平成30年10月16日改正、平成31年3月20日改正、令和5年10月19日改正)
1.基本理念
この条例では、4つの基本理念を定めています。
2.県、県民、事業者の責務
基本理念の下に、県、県民、事業者の責務を定めています。
3.差別の禁止
障害を理由とする差別の禁止について定めています。詳細は以下のページをご覧ください。
4.県の取組
県が実施する取組について定めています。
参考資料
愛知県障害者差別解消推進条例の概要
PDF [PDFファイル/211KB] テキスト [Wordファイル/55KB]
愛知県障害者差別解消推進条例の全文
PDF [PDFファイル/142KB] テキスト [Wordファイル/149KB]
愛知県障害者差別解消推進条例 啓発用リーフレット(2023年発行・事業者による合理的配慮の提供の義務化)
※リーフレットの送付を希望される方は以下問合せ先にご連絡ください。
愛知県障害者差別解消推進条例 啓発用リーフレット(2016年発行・条例全面施行)
合理的配慮の提供に関する普及啓発動画です。ぜひ御覧ください。(障害福祉課YouTubeチャンネル)
下記画像をクリックすると、動画のページに遷移します。